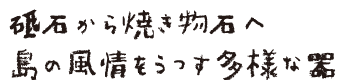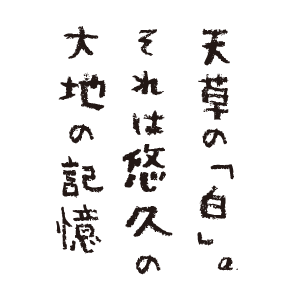
熊本県の南西部、大小120ほどの島からなる天草諸島。澄みわたる海に囲まれた島々には、世界に誇るいくつもの宝があります。その最たるものが「天草陶石」です。天草下島の西部には3本の天草陶石の鉱脈が走り、その総延長は南北約13キロにも及びます。地元はもとより、古くから有田焼や波佐見焼など各地の窯元で原材料として用いられ、日本の陶磁器文化を支えてきました。
さかのぼること、1500万年以上前。中新世期(古第三紀~白亜紀)のマグマ活動で流れ込んだ流紋岩は、温泉にさらされることで鉄分やチタンといった不純物が取り除かれ、純度の高い陶石に変わりました。ガラス質を多く含む天草陶石は細かく粉砕でき、粘りがあるために単体でも成形しやすいのが特徴です。高い温度で焼くことで強度を高めることもできるため、薄さと強さを兼ね備えたものづくりにもむいているといわれます。
採石場から切り出された陶石は人の目と手で選別され、鉄を含む量に応じて等級分けがなされます。これを細かく粉砕し、流水にさらして取り出された陶土は、どの等級を用いるかによって白のバリエーションを引き出すこともできます。また、天草陶石の陶土は、他の陶土や粘土ともよく溶け合うことから目的に合わせ、混ぜて使われることもしばしば。古くは戦国時代から、刀剣や農耕具を研ぎ澄ます〝砥石〟として九州・関西各地へ流通していた天草陶石が、〝焼き物石〟として使われるようになったのも、そうした性質があったからでした。
天草陶石が、〝焼き物石〟としての価値を見いだされたのは1662年のこと。三川内焼(別名 古平戸)の陶工・今村弥次兵衛が、佐世保の早岐港で砥石として陸揚げされていた天草陶石を発見し、針尾の網代陶石に調合させたところ、それまでよりも質の高い磁器が生まれるようになりました。石質の弱い陶石に混ぜ合わせて用いることで細工がしやすく、鉢などの大物もつくりやすくなるなど、磁器の可能性を大きく広げた天草陶石。その品質は、江戸時代のイノベーターとして知られる平賀源内が、「天下に二つと無い良品なり」と絶賛したほどです。1700年代に入ると肥前の製陶業者との間に製陶原料としての取引が始まり、平戸や有田をはじめ、西日本各地の窯元で用いられるようになっていきました。
天草における陶磁器の歴史をひもとくと、17世紀中頃に開窯した「古内田皿山窯」にたどりつきます(※)。有田・波佐見に次いで日本で2番目に古いとされるこの窯跡では、中国の明代末の染付や赤絵文様を施した磁器が数多く発掘されています。さらに1762年には、天草陶石の採掘業を営んでいた高浜村庄屋・上田傳五右衛門が、住民たちの生業をつくるために「古高浜焼」を開窯。鮮やかな絵付けを施された磁器は、オランダとの交易にも用いられました。その後、現存する「水の平焼」や「丸尾焼」などが誕生し、今では約30の窯元が島内に点在しています。
現在、天草でつくられる陶磁器の魅力を一言で表すとすれば、「多様性」という言葉に尽きるでしょう。多くの産地が藩の御用窯として発展してきたのに対し、天領(幕府の直轄地)だった天草では、島民たちが自らの暮らしのために焼く器がほとんど。今でも、透明感のある白磁から染付磁器、島の土と島の木灰を使ったぬくもりのある陶器など作風はさまざまですが、それぞれの視点と手法で天草の風情を映していることに変わりはありません。
2003年に日本の伝統工芸品の認定を受けた天草陶磁器。同年より、陶磁器を核としたイベントが行われるほか、島内外の企業とのコラボレーションが始まるなど、その可能性はさらに広がっています。